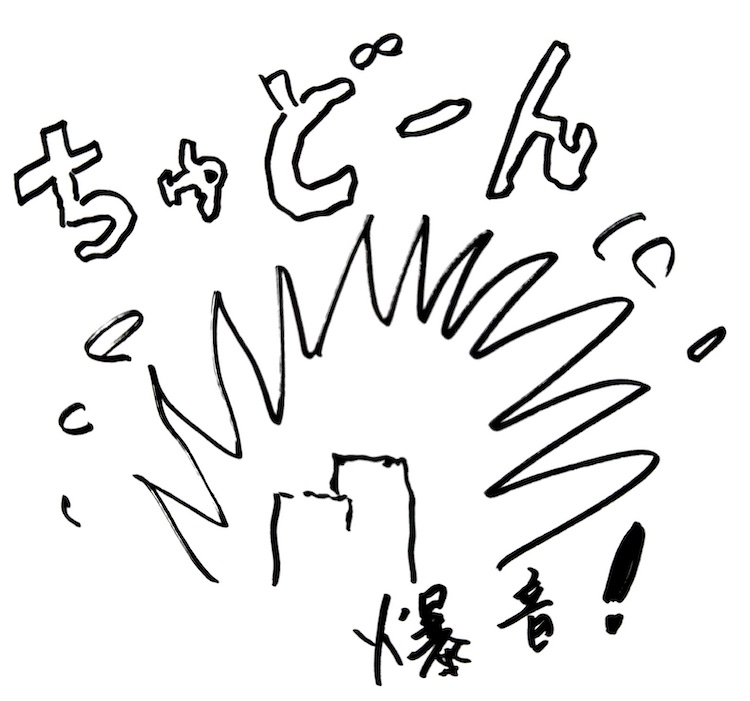2017.8.15 06:19/ Jun
「分析も解釈もできない断片たち」の何とも言えない読後感!?:岸政彦(著)「断片的なものの社会学」書評
不思議な本を読みました。岸政彦(著)「断片的なものの社会学」です。著者は、膨大な聞き取り調査をもとにして、マイノリティのアイデンティティや生活世界の諸相に迫ろうとする気鋭の社会学者です。
本書「断片的なものの社会学」は、その著者が、反社会的勢力の関係者、路上生活者などのマイノリティにインタビューを行ったデータをもとに、その生活が、淡々と描かれている書籍です。
聞き取り調査とマイノリティ・・・単に、そうしたアプローチをとる書籍なら、他にもたくさんあるのかもしれません。しかし、本書は、その「描かれ方」が「極めて独特」です。
著者は冒頭、「本書では、私がどうしても「分析」も「解釈」も「できないこと」をできるだけ集めて、それを言葉にしていきたいと思う」と宣言し、その断片を「断章」のごとく、本にちりばめていきます。
マイノリティの言葉に強く共感するのでもなく、はたまた理解しようとするのでもなく、「ただただ、そこにある」ものとして、淡々と、「それぞれの断片」を「ふつうの人々の物語」として読者の前に魅せていきます。
そして、なぜか、その言葉が、読者のこころを打ちます。この読後感は、第三者が、なかなか文字にあらわせない。ぜひ、書籍を手に取ってみていただければなと思います。「分析も解釈もできないこと」を恥じるのではなく、そこから心をうつテクストを編んでいく、という発想が、非常にクリエィティブです。
一般的な社会学の書籍は、その「真逆」をいくはずです。
冒頭、高々と、自分が依拠するパラダイム、認識論、方法論、メソッド、理論枠組みを「宣言」して、切れ味鋭い、それらの「武器」を縦横無尽に駆使して、事実・現象を「分析」し、「解釈」し、「どうだ!」とテーブルの前に提示してみせる。
研究者が「高らかに宣言を行えば行う」だけ、読者と研究者のあいだには、「知るもの」と「知らないもの」という非対称の権力構造が見え隠れします。ところが、くだんの書籍には、そうした「気負い」がありません。
本書を「社会学」と呼ぶかどうかは、門外漢の僕は知りません。また、僕は「学問の境界論議」に、興味は1ミリもありません。
しかし、僕は、この文体が好きです。そのことだけは間違いはありません。
▼
僕も、なんちゃってではありますが、物書きのひとりです。過去15年、累計すると、これまで25冊以上の書籍を編んできました(章だけの担当をいれると、書籍数は、もっと増えると思います)。
25冊など諸先輩のご努力に比すればたいしたことはないのですが、まぁ、それだけの本を書いてきて、最近、つくづく思うことがあります。
それは、
「文体を変えて、まったく、新しいものを生み出したい」
という思いです。
「文体を変える」ということは、おそらく「思考の形式を変えること」です。ですので、僕は「自分の仕事のあり方」を「ズラ」して、「新しいものを生み出したい衝動」に満たされているのかもしれません。もう一度、「なりふりかまなわない自分」に戻り、「新たな文体」をつくりだしたいのかもしれません。
文体を変えたい!
これは、僕が、ここ数年、自分の近しい編集者の方々に、吐露している悩みでもあります。
いや、ほんと(笑)
ここ1年ー2年、そんなことを考えていただけに、なかなか、この本は「刺さり」ました。
著者のような表現形式を拝見し、自分も、自分のあり方をもう一度見直したいと感じました。
おすすめの一冊です。
そして人生はつづく
最新の記事



 ブログ一覧に戻る
ブログ一覧に戻る