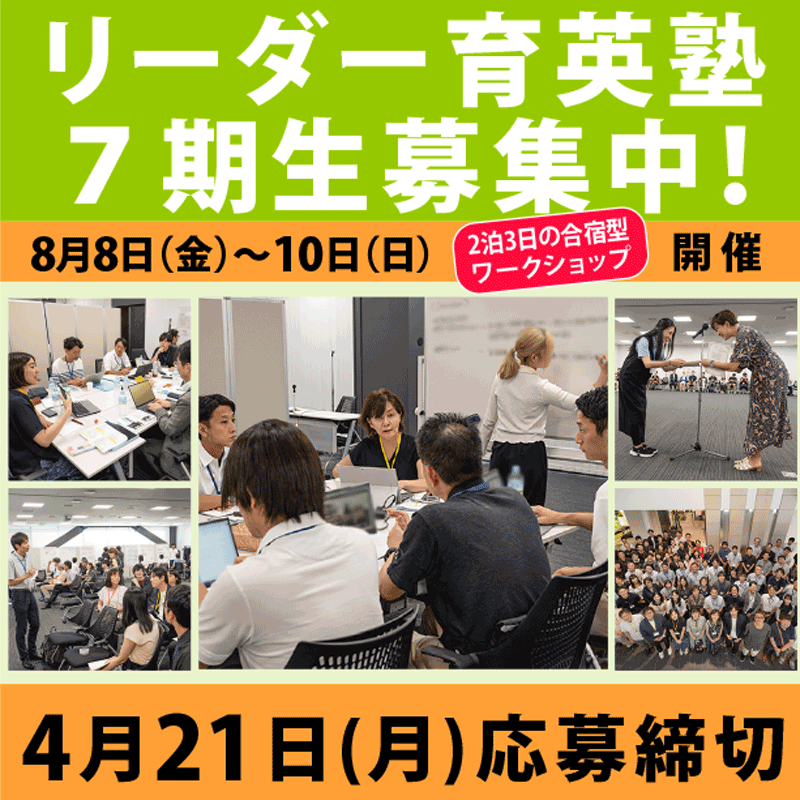2016.10.31 06:59/ Jun
一般化するな、まとめるな!、ディテールをそのままとってこい!
先日、研究室の大学院生、辻和洋君との論文指導の際、非常に興味深い話になりました。
論文指導からは話が大きく脱線して(笑)、彼がかつて某新聞社で仕事をしていたときのことに話が及んだのです。
何を隠そう(!?)辻君は、かつて某新聞社で記者として働いていたのですが、雑談の合間で、このことに僕は興味を持ちました。
辻君、あのさー
新聞記者って、どうやって、記事かけるようになるの?
新聞記事の書き方を、どのように「教えられる」の?
僕は、寝ても、覚めても、メシを食っていても、風呂を入っていても、どうも、この類の「問い」ばかり、一日中考えているのです。24時間、起きている限り、こればっかり(笑)。
辻君の答えは、こんな類のものでした。
詳細は、きっと本人が何かで書いてくれると思うのですが(論文執筆に疲れたときなどに?)、こんなことをおっしゃっていた、と記憶しています。
先輩に、ひたすら原稿をだして、つっかえされるだけです。
とにかく言われるのは、「ちゃんと、ディテールをとってこい」ということです。
楽しかった、嬉しかった、おいしかった、とか、そういう言葉で丸めるな、と言われるんです。
それじゃ、記事はかけない。
ディテールをとってこい、と言われるのです。
この答え、大変興味深いものでした。
それは、僕が、まだ学部生の時代に、指導教員の先生に何度も何度も指導されたことと全く同じだったからです。
▼
思い起こせば、今から20年以上前。
学生時代やったフィールドワークで、徹底的に、当時の指導教員の先生に指導されたのは、
「一般論でくくるな、固有名詞で情景を把握しろ」
「プロセスを見ろ」
ということでした。
当時は、エスノグラフィーやフィールドワークといった定性的な研究手法が人文社会科学に導入されたばかりの頃で、専門書も大変少なく、みな、見よう見まねで、それに取り組んでいました。僕も、そのひとりであったのです。
当時の指導教員のおっしゃっていたことは、辻君がおっしゃっていた「ディテール」に近いものである気がします。
曰く、
見たもの、聞いたものを「一般化」するんじゃなくて、どんなにベタベタ・ドロドロでもいいから、出来事を書いて、そのままもってこい、と言われました。
「Aさんは・・・あのとき、していて、こうなった」
というディテール、プロセス、出来事を記述するように繰り返し、繰り返し、僕は指導されました。
「起こった出来事を、頭の中で、勝手に一般論にまとめるな」
「出来事をそのまま書いてもってこい」
と厳しく指導されたことを思い出しました。
どちらかというと、当時の僕は「頭でっかちなところ」が今よりも多々あり、こうした先生のリクエストにこたえることは、なかなか難しいものでした。
忙しい先生に研究をもっていくのだから、なるべく短く箇条書きにして発見事実をもっていきたい、という頭もあったのかもしれません。そういう「知的」な作業を先生にみせることで、僕は褒められたかったのかもしれません。まぁ、ディテールを一般化してもっていくと、まったく「褒められない」のですが・・・(泣)
ともかく、このリクエストにこたえるのは、大変苦労した記憶があります。
が、しかし、今から考えれば、それは大変ありがたいご指摘でした。
なぜなら、「ディテール」がなければ、本当に「書けない」からです。
今から考えれば、アタリマエのことなのですが、出来事やプロセスが記述できていなければ、エビデンス(根拠)を示したことにはなりません。
エビデンスがないものは、論文には絶対にならないのです。
先生、丁寧なご指導に感謝いたします。
▼
今日は新聞記者の新人指導の話を皮切りに、定性的な研究手法のお話をしました。
まぁ、まったく似ても似つかない両事象ではありますが、そのふたつは、一面、とても似ているな、と思いました。
辻さんは、今、修士課程2年目。
修士論文の執筆のプロセスにいます。今が、たぶん、一番苦しい時期です。
手前味噌になるかもしれませんが、彼の修士論文は、丁寧に、そして、根気よく「書き抜くこと」ができれば、素晴らしいものになると思っています。
「終わった論文」が「よい論文」。
僕は、書き終えた「彼の論文」が楽しみです。
そして人生はつづく
−−−
追伸.
新刊「アルバイトパート採用・育成入門」発売中です!。これまで「KKD:勘と経験と度胸」に頼っていた、アルバイト・パートの人材育成。ここにデータと理論で切り込みます。異業種・大手7社、総従業員規模50万人以上の企業グループが参加した東大・中原淳研究室とパーソルグループの共同研究の成果。ぜひ手に取ってご覧下さいませ!
最新の記事



 ブログ一覧に戻る
ブログ一覧に戻る