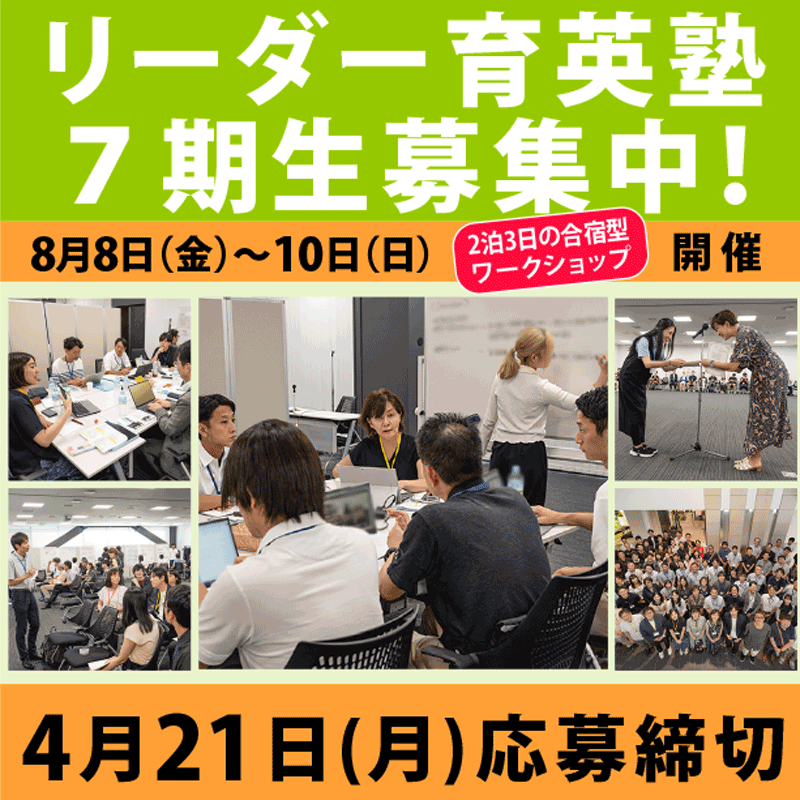2011.2.10 10:34/ Jun
モード1とモード2の「狭間」で:マイケル・ギボンズ「現代社会と知の創造」
マイケル=ギボンスの、いわゆる「モード論」を、夜な夜な、ふとんの中で読み直していました。この本、大学院を出るかでないかの頃に、一度、読んだ記憶があるのですが、そのときはあまり「ピン」ときませんでした。
でも、それから10年。
今あらためて、35歳になって、センターでの教育企画の仕事に携わりながら、教育・研究活動を大学において行い、研究室を運営し、この本を読み直してみると、なかなか興味深いものがあるな、と感じました。
自分の研究の置かれている立場、大学に期待されている社会的役割。
ギボンズの提示している「枠組み」を「鵜呑み」にするのではなく、それを「たたき台」にして、自分の10年間の活動、目にしたもの、耳にしたもの、を振り返ってみると、少なくとも「ピン」とくるのです。「そうだよな」と思わず「首肯」してしまうところや、「違和感」を感じるところがでてきました。
▼
いわゆる「モード論」の著者マイケル=ギボンズは、現在の科学技術の研究活動、いいえ、それのみならず知識生産の様式(モード)を敢えて戯画的に類型化し、「モード1」と「モード2」という呼称を用いました。
一言でいえば、「モード1」とは「個別の研究分野・研究方法論(ディシプリン)中心型の学問」のこと。いわゆる「モード1」を「サイエンス」とよみかえれば、もしかすると誤解をたくさん生むかもしれませんが、わかりやすいかもしれません。
これに対して、「モード2」は、「個別の研究領域・研究方法論に依存しない、領域越境型の科学であり、実世界と深い関連をもつ問題を発見し、その解決をめざす学問」です。
なお、「モード1」と「モード2」は、敢えて極化・戯画化して描かれていますので、違いが明瞭でわかりやすいです。しかし、その反面、その概念が多種多様な批判にさらされていることも、まず最初に述べておきます。
そのことを含み混んだ上で、ギボンズが提示した「モード論」とは、どのような概念的フレームワークだったのでしょうか。「モード論」は科学技術社会論、産学連携、社会貢献のコンテキストにおいてよく引用され、専門的な議論が行われているのでしょうが、僕は、圧倒的「専門外」です。ですので、それに甘えて無責任にあえて「簡略化」します。それは下記のようにまとめられるのかな、と思います。
▼
【研究の問題設定】
■モード1
・問題設定は、各研究分野の内的論理によって行われる。
いわゆる基礎研究や学術研究を支配する認知的・社会的規範
と関連づけて行われる。
■モード2
・産業的応用、社会的応用の中で行われる
・「誰にとって役立つか」という点が意図される
・「なすべき価値」が自明ではないため、研究に自己言及性
が生まれる
—
【研究活動の主体】
■モード1
・単一のディシプリンをもつ大学研究者
■モード2
・大学研究者のみならず、産業界・政府の専門家
市民など多様な人々
—
【研究活動組織】
■モード1
・大学の中にすでに制度的に安定的に位置づけら
れている組織
■モード2
・非階層的で非均質的に組織された形態。大学意外の
研究機関、シンクタンク、政府機関なども該当する。
それらが電子的・組織的な多様な手段・メディアで
結ばれることでコミュニケーションが機能する
—
【研究活動の推進】
■モード1
・単一のディシプリンの方法論による解決が行われる
■モード2
・多様なディシプリンからの参加が求められる
ディシプリンを調節したトランスディシプリナリーな
問題解決が行われる
・知的生産のすべての過程で多数のアクター間に緊密な
相互作用がある
—
【研究成果の価値】
■モード1
・各研究分野の知識体系にいかに貢献しているかで決まる
■モード2
・研究成果は必ずしも個別ディシプリンの知識体系の発展
に貢献しない
・知的生産の成果が社会的なアカウンタビリティを
獲得しえるかどうか
—
【研究成果の発表】
■モード1
・学術雑誌・学会などの制度化されたメディアで行われる
・同じ研究方法論の同僚研究者からのピアレビュー
■モード2
・成果は参加者が研究活動に参加している最中に伝えられる
研究の成果発表は、研究活動の中に埋め込まれている。
参加者が別の問題コンテクストに移動していくことで、研究
成果が移転する。
▼
くどいようですが、僕はここで「モード論」をとりあげたからといって、この「ダイコトミー」に満足しているわけではありません。
また、ここで「モード1とモード2のどちらかが優越する」という議論をしたいわけではありません。加えて「モード1とモード2のどちらかのあり方を、他者に迫ることは本意ではありません。
あたりまえのことですが、厳密な意味で「モード1」と「モード2」を分けることはできません。そのことは、ギボンズも指摘しているように、「伝統的なディシプリン教育を受けた人、つまりはモード1をなした人が、モード2に移行すること」からも明らかです。
▼
ただし、一方で、本当にしみじみと実感するのです。
今、大学は、程度の差こそはあれ、この「モード1」と「モード2」の「葛藤」・「制度的矛盾」の中にあるよな、と。
「モード1」と「モード2」の境界において生まれる制度的矛盾に、時にあがない、時に揺らぎつつも、一方で何とか、この「バランス」や「折り合い」を、必死に組織的にとっていこうとしているように、僕には感じます。
そして、僕のような研究分野で(他の分野はわかりません)、現在の大学において教育・研究活動を行うということは、この矛盾や葛藤の中に、程度の差こそはあれ、影響を受けることなんだろうな、と思います。
▼
ギボンズの「モード論」は科学技術論の中で消費され、語り尽くされ、論争のまとになりました。それはギボンズが「モード2」に肩入れをしていたことと無縁ではないように思います。著書の中にもありますが、「こんなものは研究ではない」というような批判も生まれ、のちのちの科学技術論においては、これを乗り越える努力がなされています。
しかし、僕にとっては、一定の「自省を迫るメディア」「自省をうながすテクスト」として、本書を読むことができました。
かつては「ピン」とこなかった科学技術論ですが、この年になってみると、これは「自分の問題なんだな」と思うようになっているようです。これが「成長」なのか、「老化」なのかはわかりませんが。
「モード1」と「モード2」
いずれにしても、僕は、その葛藤と矛盾の中にあります。
そして人生は続く。
—
■2011年2月9日 中原Twitter
- 18:14 (2)”Ba” Design Talk Live : WS、社内コミュニケーション、勉強会、朝活、セミナー、講演会、研修、勉強会、読書会、異業種交流会、インナーコミュニケーションなどに興味をお持ちの方、参加なさっている方、におすすめでーす。http://ow.ly/3SZ1a
- 18:14 (1)ブログ更新。”Ba” Design Talk Live 2月25日(金)午後7時 UST無料中継。知がめぐり、人がつながる場のデザイン」について、ゆるくお話しできると素晴らしいことですね。http://ow.ly/3SYZc
- 17:41 興味深い>RT @lilaclog GDP世界一の都市・東京 – My … http://htn.to/pepKRX [in reply to Lilaclog]
- 17:29 3日間のデジタルストーリーテリングワークショップを、大礒さん、重田さん、大房さんらと一緒に、東大でやることになった。研究にもできそう。楽しみです。
- 11:22 興味深い>「ブクブク交換会」テーマを決めておすすめの本を持参し、名刺を挟んだ本と本を交換する新しい日常の中のエンタメ RT @tomokihirano おもしろそう。本と名刺の交換会「ブクブク交換」公式サイト http://bit.ly/h3RDtc [in reply to tomokihirano]
- 09:58 伊勢坊さん(中原研M0)TELにて研究相談。研究テーマは「秘書の熟達化」:秘書は、どのようにして一人前になるのか?
- 09:43 日本医療教授システム学会(@JSISH)は、3月あたりに「医療職の能力開発」という学術雑誌を創刊する予定です。編集長は東京大学の大西弘高先生(東京大学医学教育国際協力研究センター)。中原も、ひそかにちゃっかり、なにげに、この学術雑誌の編集委員の末席に加わっています。
- 08:13 面白い。あなたのタイムラインが「新聞」になる。一覧表示は便利かも。@tomokihirano 自分のTLをまとめてオンライン新聞を作ってくれる。paper.li 日本語対応。The Tomoki Hirano Daily http://bit.ly/eJXAaB [in reply to tomokihirano]
- 07:34 デジタル教材を使いさえすれば、教育効果があがるか?@yuuhey ブログ更新:デジタル教材の評価・よくある誤解 http://t.co/ZzurvbG [in reply to yuuhey]
- 07:28 中小企業、今春4月入社の大学生を、今なお採用。内定率低迷でこれまで獲得できなかった新卒採用に力をいれる(日経)
Powered by twtr2src.
最新の記事



 ブログ一覧に戻る
ブログ一覧に戻る