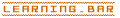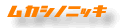「穴埋め問題としてのアート」、この、不幸せな出会い!?
僕の場合、生まれてはじめて美術館に出かけたのは、記憶に残っている限り、高校生くらいのことだったように思います。「高校生くらい」と書いたのは、それさえも、確たる記憶にないのです。もしかしたら、中学生の頃だったのかもしれませんし、高校生の頃だったのかもしれません。
ひとつ間違いのないことは、生まれ故郷にある公立の美術館には、記憶に関する限り、一度も行ったことはなかった、ということです。
のっけから、自分の「文化資本の低さ」を露呈するようで、いささか気が引けるのですが、それも、仕方がありません。過去や生まれは、変えることができません。
小生、子ども時代から、アート、美術、芸術とは全く「縁遠い」生活をしてきました。そのことを、なんでだったのかなぁ、と今になって考えることがあります。
▼
アート、美術、芸術というよりも、子ども時代の僕にとって、まだ身近であったのは「図工」であったように思います。しかし、かつての僕は、完全に「誤解」をしていました。
つまり、図工も、どこかに「正解」があるものだと思っていた節があります。図工の鑑賞には、「この作品には、こう答えておけば、無難な答え」が存在し、それを暗記することが「鑑賞」なのだと。
僕の予感は、
「ゲルニカとは・・年に制作され、作者は・・であり・・・の影響を受けている」
という命題に対して、回答を求めるような「穴埋め問題」が、定期テストに出題されたことをもって、「確信」にかわりました。
要するに、ここまでをまとめると、アート、美術、芸術と僕は、「幸せな出会い」をしていなかったように思います。
今だったら、「アート作品の穴埋め問題」を見て、
この問題こそが、"現代アート"ではないか!
と叫んでしまい、拍手喝采してしまうところですが、そういう余計な智慧と皮肉は、当時の僕は、持ち合わせていませんでした。
▼
上野行一著「まなざしの共有」を読みかえしました。
本書では、対話型鑑賞の主導者であり、かつてニューヨーク近代美術館で実践を積み重ねてきた「アメリア・アレナス」の概念・手法を紹介し、対話型鑑賞についての理解を深めていきます。
アレナスの実践で、重視されているコンセプトは、
「芸術とは、作品の中に込められているものではなく、作品と私たちの関係である」(p48)
という考え方です。
ロラン・バルトが「テクスト」と「作家」の特権的立場を批判し、「テクスト - 読み手」の関係性を問うたように、アレナスにおいても、芸術を「見るもの」へと開放させます。
この対局をなす考え方は、
「作品の中には、作家が込めた意味や理論がたくさん詰まっていて、それを読み取ればいい」
とする作品観ですね。
こちらは、先ほどの、子どもの頃の僕の美術観に似ているような気もいたします。
かくして、彼女は、作品を前に、鑑賞する人々に問いかけます。静謐を旨とする美術館に対話が生まれます。
「この作品について話しましょう。これは何でしょうね?」
「この作品では、いったい、何が起きているの?」
「何を見て、そう思ったの?」
対話型鑑賞とは、この一連のコミュニケーションの連鎖の中に生まれます。
▼
本を読みかえし、つくづく思ったのは、「子ども時代に、アートと、こうした出会い方をしたかったな」ということです。
「学校教育の研究」を離れて10年以上立ちますので、僕は、現在の状況がどうなっているか、知りません。また僕は美術や芸術の専門家ではないので、専門的議論や乗り越えられるべき課題は知りません。
おそらくは、僕のような「果てしない誤解」をしている子どもは、少なくなっていることと思います。
それにしても、
子ども時代には、
事物と「よい出会い」をしたいものです。
そして人生は続く。
投稿者 jun : 2013年5月15日 08:57
【前の記事へ移動: キャリア教育とは言わないキャリア教育、越境学習とは言わない越境学習:電子書籍「東 ...】【次の記事へ移動: 「今、ここの出来事」がコンテンツ化するということ:タブレットを持ち歩くようになっ ...】