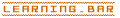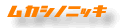モデルとは何か?
教育工学会1日目。
実践研究に関するシンポジウム。
シンポジウムの議論を聴いていて、とても気になったのは、「実践の設計モデル」の「モデル」という言葉について。
このシンポジウムでは、登壇者の先生方が、「いくつかの教育実践に通底する共通点を抽出して、実践の設計モデルを構築すること」について、異なった角度から議論していらっしゃった。
先生方のご発表は大変興味深いものであり、また参考になった。実践現場で得た様々なデータを「元」にものを言うことは、大変難しいことである。
▼
僕としては、先生方のご発表内容とはズレてしまうものの、この「モデル」という「言語の使用」について、一人気になって仕方がなかった。
僕の疑問は、一言でいうと下記。
モデルとは
どのような表現形式で
誰のために存在し、
どのように利用されることが
求められているのだろうか?
途中で脳裏にこの問いが生まれてしまい、結局、シンポジウムの間中、自問自答が続いた。
▼
考えてみればすぐにわかるように、この問いに対しては、いくつかの「答え」がある。
簡単に答えるのなら、「研究者がわからないことをわかるようになり、すっきりするため」というのもあるだろうし、「実践者が利用するため」というのもあるだろう。
どちらが「真」とも「偽」とも簡単には判断はつかない。この答えの是非を問うことは、 - 僕の中では答えはでているけれど - 敢えて、ここではしない。
しかし、僕自身が重要だと思うことは、教育研究から導出される「教育実践モデル」は、そのステークホルダーによって、表現形式が変わるはずだし、その粒度も変わる、ということである。
そして、さらにいうならば、「モデルを活用した普及のあり方」も変わるはずである。
▼
しかし、教育工学は「実践の学」である内部で規定しつつも、この「表現形式」「粒度」「普及のあり方」に関する配慮が十分であったとはいえない、と僕自身は感じている。否、教育工学というより、これは教育研究全体の課題かもしれない。
もちろん「わかるものをわかりたい」「ぐちゃぐちゃしているものを整理したい」という研究者的観点をもちろん否定するわけではない。それは研究者としてアタリマエの衝動であり、僕自身もその動機をもつ。
しかし、教育工学の関係者が、その学問の本質を「実践学」とよぶ限りにおいて、この研究者的観点を、そのまま実践現場に伝達するのではなく、様々な「言説転換の手段」を通じて、実践者の表現、実践者の粒度に翻訳する必要が、どうしても生じてくるのではないだろうか。
これは「アポリア」である。
逆にいうと、教育工学が「実践学」だと自己定位し、それを推進することは、「そのアポリアを引き受ける」ということであり、それを引き受ける覚悟を決める、いわゆる「腹をくくる」ということに、僕には見える。
誤解を避けるために繰り返していうが、教育工学の中で、「学びとは何か」「支援とは何か」について、「わからないことがわかるようになること」「ぐちゃぐちゃしていたものがわかるようになること」に関して、僕は研究者として違和感はない。
しかし、「タテマエとしては現場に届くことを表明していながら、届く宛先のない実践学、届くための配慮を欠いた実践学」には、僕は違和感がある。それは、誰のための「実践学」なのか?
▼
別の角度から問題を考えよう。
教育工学の研究知見は、
誰に対して
どのような形式で伝わり
どのように利用されていたのか?
もし、この問いに対して「利用されていたのだ!」と胸をはって答える人もいよう。
しかし、そのときには「モデルだけが現場に提供されたのだろうか」。おそらく、それは疑わしいのではないか、と僕は思う(それが悪いというわけではない)。
研究者が導出したモデルだけで、現場が改善するほど話は単純だろうか。本当のところ、モデルだけではなく、どのような機会が必要であったのか。そして、もし「モデル以上の機会」が必要なのだとしたら、どうして、それは「研究の一部」として語ることをOmitされてしまうのか。
今日のシンポジウムで出てきた話題の中では、「モデルを解釈するワークショップをこみにして、モデルを提唱する必要性」を稲垣先生が述べていらっしゃった。そのご指摘には、とても共感できる。
▼
学問には、学問自体のあり方を批判する学問 - 批判理論が必要だと、恩師は僕に常日頃から言っていた。
それに乗じて、自戒を込めて、否、自らの発言で、自ら痛みを抱えることを覚悟して、これを指摘する。
教育工学は、これまで「実践現場を研究対象とすれば、そのモデルはいかなる表現形式で、かつ粒度をもっていたとしても、実践者に伝わるのではないか - という「かなりナイーブな思いこみ」を持っていたのではないか。
そして、この「ナイーブさの功罪」は、今日の(明日だと思っていた!?)僕の発表内容である、
試論:教育工学は「何」を<デザイン>するべきなのか?
教育現場の持続可能な変革の支援をめざして
で、僕が主張したいことに関連すると思う。
おぼろげながらではあるが、問題の大枠が、前よりも見えてきたような「錯覚!?」をおぼえる。
---
追伸.
学会終了後、堀田龍也先生と議論する。堀田先生は、僕が「今以上にペラペラ・ペーペーであった頃」から大変御世話になっている、僕が尊敬する研究者の一人である。
印象深い一言があった。
堀田先生は、様々な教育現場で指導を行っているが、その際、与えられる時間は計5日間、計20時間くらいしか、ないのだという。
その際、限られた時間で、どのようにして学校変革を外部から支援するか。
堀田先生がおっしゃるには、「キーマンになる現場の先生をいかに見抜くか」ということが重要であるとのことであった。
このことは、先日、ある有名なコンサルタントの方がおっしゃっていたことと、全く同じだったので、その符合にびっくりした。
結局、「自分たちで自分たちのあり方を変えていける人、加えて、自分が変わろうとする人を、どのように見つけ、支援するのか」という問題につきる。
▼
来年あたり、教育工学の発表カテゴリに「学校変革」「学校改革」というカテゴリーがうまれることを願う。
組織の変革をデザインすることは、教育工学の研究範疇であるべきである、と僕は考える。
「教育工学村」を出て、さらには「教育村」の外の、「圧倒的外部、であり、世の中という、圧倒的多数のステークホルダー」の目からみて、いったい、今、何が、学問に求められているのだろうか。
もし、その「目」を意識するのなら、これまで注力してきた「モノのデザイン」「環境のデザイン」に加えて、「組織のデザイン」「組織間のデザイン」があるように思う。少なくとも、まずは理論的考察やその是非に関する検討が行われてもよい。
問いは深まる。
僕は、「遅れてきた思春期」かもしれない。