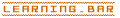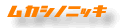大学院の「研究室」!?
大学院の「研究室」というのは存在しない。
といったら、訝しがる方もいるだろう。
もちろん、大学には物理的、空間的に「研究室」、つまり「部屋」は存在する。僕がここで言いたいのは、そういうことではない。
ここで僕が「存在しない≒想像の共同体である」とみなせるのではないか、と主張しているのは、
東京大学大学院 学際情報学府 中原研究室
という類の、「○○研究室」とよばれる集団のことである。
多くの大学院生が、「自分は○○研究室に所属しているぞ」と思っている。つまり、確固たる「所属組織」として「○○研究室が存在しうる」と感じていると思う。
しかし、この○○研究室というものは、法的にはもちろんのこと、多くの大学においても制度的に位置づけられたものではないと思う(もしかすると、それは僕の関係する大学院だけかもしれないので、確信はない・・・以降の議論は、少なくとも、僕の関係する大学院では、という前置きをすべての文章において必要とする)。
むしろ、どちらかといえば、慣習的に「○○先生の研究指導を受けている人たちの集団」、あるいは「研究指導を行うゼミの名前」を、そう呼んでいるだけであることが多いのではないかと思う。
○○研究室が法的にも、また、制度的にも位置づけられたものでないという可能性を有するということは、その「際」、つまりは「研究室とウチとソトをわける境界」も本来非常に曖昧だということである。
教員によっては、自分の共同研究者、あるいは、自分の研究にゆかりをもつ人々までをメンバーに含めて、「○○研究室」と呼んでいる人もいる。
さらには、何をするか、も別に法的、制度的にきまっているわけではない。つまり、目標も活動方針も所与のものではない。
つまり、そこには「明確な境界」がないことに加え、「メンバーシップの基準」も存在しない。「共有する目標」も、「活動」も、所与のものとして決まっているわけではない。すべては、研究室ごとに「決定」されるべきことがらである。
「大学院の研究室」とは、そういう「不思議な組織」である。
こんな不思議な組織をどうやってマネジメントするか。大学院の教員の中には、そのことに苦心している人も多い。
▼
僕は経営学者ではないので、研究室のマネジメントについて、確固たる手法をもっているわけではない。
一般に営利組織のマネジメントよりも、非営利組織のマネジメントの方が、独特の難しさがともなう。研究室は、その最たるものだと思う。
でも、少ない経験と教訓をもとに、ひとつだけ言えそうだな、と思うのは、研究室に所属するすべてのメンバーが、研究室全体、あるいは、研究室のメンバーがなしとげたいと思っていることを、「自分のこと」として理解し、時には手をさしのべ、ときには健全な批判や支援をなしうること、である。
一言でいうならば、「相互に貢献しあう関係」「相互に学び合う関係」が必須ではないか、ということである。そういう意識を、研究室のメンバーがいかにもちうるか、ということである(もちろん、これは、どの研究室にもあてはまることではない。少なくとも、僕に関する限りは、という限定付きで、そう思う)。
自分は、「学生」なんだからサービスの受け手。「研究室」はあってアタリマエ。教員は何かをしてくれてアタリマエ。「誰か」が何かを与えてくれてアタリマエ、といった「お客さん意識」では、想像の共同体は、それこそ「想像の中」のものになってしまう。
研究室とは、知的興奮にあふれる一方、常に「揺れている」。
あなたが他者に何かを為し、為される関係。あなたが学び、あなた自身が学ばれる関係の中に、それはある。