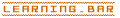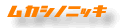何を見て、何をなすべきか?
今、仮に、アメリカの教育現場に視察に行った一群がいるとしよう。話をそこからはじめる。
どこぞのエライセンセイが団長になって、何名かの教育研究者を中心に視察団が組まれる。バジェットは、国であったり、企業であったりする。
視察団のメンバーのひとりが、現地の大学教員やコーディネータと連絡をとり、彼らをカウンターパートとしてスケジュールを決める。視察団のメンバーは、現地の人々から紹介されたいくつかの学校を回る。
そこで見る「アメリカの教育」は、コラボラティブで(Collaborative)、シリアス=ファンで(Serious Fun)、民主的で(Democratic)、いわゆる教育研究者が夢見がちな「教育の理想」である。
彼らは帰国後、シンポジウムやフォーラムなどをひらき、熱意とロマンティシズムをもって、「アメリカの教育」を扇情的に語る。
「アメリカでは・・・教育は○○のようである」
「アメリカの教育は・・・である」
聴衆はすっかり「魅了」される。そして、いつしか、自国の教育を、それとは対置した「時代遅れのもの」として語るようになる。「魅了」はいつしか「焦り」に変わることもある。
このような「情景」は、日本の「ここあそこ」で繰り広げられている。この手のシンポジウムに対するニーズは、不思議なほど高い。「外国では○○だ、だから日本は○○すべきという"では系・シンポジウム"は、なぜかどこも大入り満員である。
---
2004年、アメリカに留学する前の僕は、そのようなシンポジウムやフォーラムで語られる「アメリカの教育」を、あまり批判的に見ることのできない一人であった。
しかし、留学後、一般論として「アメリカの教育」を語ることには相当慎重にならざるを得ないことを、僕は、他ならぬアメリカで、この目で学ぶことになる。
たとえば、今、日本から視察団がくる。現地のコーディネータによって紹介される学校は、いわゆる「見栄え」のするものであり、いわゆる「ハイエンド」の、政府や民間企業からの資金が豊富にあり、教員の資質も高い学校である。
もちろん、授業は、コラボラティブで(Collaborative)、シリアス=ファンで(Serious Fun)、発見的である。彼らにとってそれは、理想に見える。
しかし、その数キロ先では、ドリル&プラクティスが中心の一方向的な授業で、全員が一度に席につくことすら希な学校がある。
多くの生徒がマルチカルチャルな背景をもち、片親で、貧困にあえぎ、学校の窓には鉄格子がついている。
これは極端な例もしれないけれど、実際にツテをたどって、自分の足で、何校か学校を回ってみると、それは日本の学校ほど均質化しておらず(よい意味で使っている)、「同じ学校だよねー」とひとくくりでなかなか語られないことに気づかされる。
アメリカにある学校は、決して「アメリカの教育」として「ひとくくり」にはできないことに、厭でも気づかされる。
学校が存在する地域の事情、そこに集う人々の社会的背景や文化的背景・・・様々な社会的要因が絡み合うところに、「学校」がある。もちろん、どの場所で行われている教育も「アメリカの教育」である。しかし、ハイエンド以外の教育現場は、決して「アメリカの教育」として語られることがない。なぜなら、教育研究者は、それを「見ていない」から。
自戒と懺悔をもって明言するなら、視察団の中には、アメリカの学校が100校あったとしたら、その1%、いや0.1%にも満たない「ハイエンド」をもって、「アメリカの教育」を熱意をもって語っていることも少なくない。
▼
もちろん、視察団が見た「アメリカの教育」も、その「一面」である。限られた時間の中では、限られた情報しか得られない。それはやむなきことである。しかし、「アメリカの教育」を語るとき、そこには、実際にはたくさんの「括弧がき」があるはずである。
わたしの見たものは、(ボストンの、比較的裕福な地域の、多くの親が大学関係者である)アメリカの教育現場である
という風に。
その「括弧がきの中身」が漂白され、さらには過剰に一般化され、「アメリカ」として語られるとき、そこには本来「語り得ぬもの」を「語っていること」に、どれだけ、わたしたちは - 否、僕は、自覚的であり得たか。そのことを、どれだけわかっていたか。
▼
いったい「アメリカの教育」とは何なのか?
なぜ、視察団である自分たちは、「アメリカの教育」として、「ハイエンド」を見ざるをえなかったのか?
さらに厳しく問うならば、
教育研究者、否、僕が見ることのできる「現場」とは、いったい「何」なのか?
さらには、そもそも、外部にいる僕には「現場を見ること」ができるのか。
話のきっかけは、たかが「アメリカの視察」の話だったけど、ここには、実は、「研究者と現場」をめぐる、「底なし沼のような問い」が隠されている。
---
正直にいう。
最近、僕はわからなくなってきている。
大学院を出てから数年間は、少なくとも研究の方向性について「悩みらしきもの」はなかったのだけれど、ここにきて、30を過ぎて、どうも、僕にはわからなくなっている。
その「わからなさ」を一言で述べるならば、
「どのような現場を見て、どのようなテイストの知見をだしていくことが、教育研究者として、 - 否、一般的に、教育研究者がいかに仕事をするべきか、など僕には興味はない - 他ならぬ"僕"としては、納得できるのか」
ということである。
少し現場の人と話せば、現場に通常身をおくことのない僕にとって、ハイエンド以外の教育現場を目にしたり、耳にしたりする機会がそもそも閉ざされていることに気づかされる。
つまりは、僕が目にしているものは、「現場の一部」であって、「現場のすべて」ではない。僕は「現場の人」ではないから、それはある意味で仕方がない。
加えて、大学や研究の現場では、常に「オリジナリティ」が求められている。
だから、「今現在、どんなに現場で課題になっていること」であったとしても、「過去に一度でも考察され、過去に先行する研究が存在」していれば、二度と同じかたちで、それを行うことはできない。
否、してもいいけど、それは「コンサルティング」であって、いわゆる「研究」としては認められない傾向がある。だから必然的に、「ハイエンド」を追い求める宿命にある。
ここで二つの選択肢がある。
「ハイエンド」を見て、それを分析・研究し、「これからはこうなる」と「さらにハイエンドな教育現場」を提案したり、その成功要因を明らかにしたりすることが、僕に求められていることなのか。否、僕がやりたいことなのか。
いや、違う、「ハイエンド」ではない、残りの99%の普通の、一般的な、ハイエンドではない教育現場で、「今、求められていること」の処方箋を現場の人と考えることが、僕のやりたいことなのか。
どちらも、それなりの理屈はとおる。
「大学とは、学問とは、カッティング・エッジな研究や実践を通して、未来を提案するべきである」
あるいは
「大学とは、学問とは、今、現場で課題となっていることを考察し、処方箋を提供するべきである」
心ある研究者にとっては、あまりに「初歩的な問い」なのかもしれないが、正直、僕には今、踏ん切りがつかない。時に右にふれ、時に左にふれる。ここが、僕はどうも一貫していない。
もちろん、一貫性は保つ必要はないのかもしれない。矛盾や葛藤を自覚しながら、両者を抱えることしかないのかもしれない。
しかし、いずれにしても、まだ僕はどの選択肢に関しても、「メイクセンス」していない。それには、もう少し時間がかかりそうな気もする。
なんだか、最近、モヤモヤとしている。