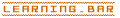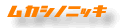わからないことを教える!?
大学院の研究指導とは難しい。「指導」という言葉から、「わからないことであっても教えること」を暗に求められるからである。
アタリマエのことではあるが、それぞれの大学院生が抱えている課題は「研究課題」である。「研究課題」ということは、原則として、全く同じ課題に過去に取り組んだ人がいないということであり、結果が「わからないこと」である。結果が「わかっている」なら研究ではない。「わからないから研究」なのである。
もちろん、教員とて「研究の結果がどうなるか」はわからない。意外に知られていないけれど、研究とは「教員も結果がわからないこと」なのである。
もちろん、教員側には若干の「経験」「テクニック」「クソ度胸」がある。これらを駆使すると!?、課題の結果が「全くわからない」かというと、不思議なもので、何となくおぼろげながら「予測」はつく。
しかし、予測は予測。「結果がでるだろうなぁ」と思ったのに、「分析の結果はあれーどしちゃったの」だったり、「こりゃ無理だろ」と思っていたのに、「なぜか、うまくいったわ」なんてことは日常茶飯事である。僕の「経験」や「テクニック」が「ショボイ」せいでもあるかもしれないけれど。
というわけで、「研究指導」というと「教え導くもんねー」という感じだけれど、この言葉には、僕はどうしても「違和感」がある。教員は「知っている存在」で、大学院生は「知らない存在」というダイコトミーがどこかに見え隠れするからである。
むしろ、教員のやっていることは「わからないこと」を前に、学生と一緒に討論し、彼が仮説を練り上げたり、意思決定をすることを助けることに近いように思う。をあるいは、「研究って楽しいぞー、こうやりゃいいのかもしれねーぞー」ということを、「研究する自分」を通して見せることに近いように僕は思う。
「わからないことを、わかったふりをして教えることはできない」。まして「教員が仮説を練り上げ、意思決定をするなら、それは教員の研究である」。もちろん、「やる気がない人にやる気をつけてあげる時間はない」。
---
今日は、大学教員を例に話を進めてみた。しかし、賢いあなたならもう既に気づいたとは思うけれど、大学教員以外でも、かなりの職業が、実はそういう性格をもっている。
マサチューセッツ工科大学の組織学習研究者、ドナルド=ショーンは、かつて「The reflective practitioner」の中でこう言っていた。
プロフェッショナルとは、「自分が学んだことのない仕事」「教えられたことや教科書の枠には当てはまらないスキマの仕事」を行う。
ショーンによると、「眼科医の場合、患者の多くは教科書に載っていない問題を抱えているという。症例の80%くらいは、自分が慣れ親しんだ治療や診療にあてはまらない」そうだ。
ということは、眼科医を育てる眼科医の場合、自分も完璧にはよくわからない事例にぶちあたることはよくある、ということになる。そういう場合には、「わからないこと」を前に、若い眼科医と一緒に事例を検討しなければならない。そういう場合には、「仮説をたて、検証しつつ、意思決定を行うことを支援する」他はない。
---
世の中わからないことだらけである。そして「わからないこと」にアタックする人を育てる側も、また「わからないこと」だらけである。
キチンと目標を定義して「教えられること」がたくさんあればいいのだけれども、実はそう多くはない。
でも、「わからない」から教える方もオモシロイ。
これもまた事実である。