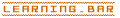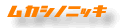語り得ぬものをいかに伝えるか?:ワークショップ的?採用面接
「現場をまわる」
企業人材育成、組織学習の研究に本格的に着手するにあたり、密かにそんな目標を立てた。
僕は「学生」からそのまま「教員」になった。いわゆる「大学の外の世界」を知らない人間である。そういう人間が、この研究を人並みにこなしていくためには、現場を徹底的に知る必要がある。「会社を知っている人」なみ、否、それ以上に、いろいろな「現場」を見て聞いて感じなくてはならない。
1月にヒアリングさせていただいた会社数は約20社。どこの現場も、現場にかかわる方の話も、本当にリアルで面白かった。フィールドノーツを書くのが、大変である。
---
今日は、アルバイトの採用に徹底的にこだわる会社 - 仮にA社とよぶ - を訪問させていただいた。A社では、アルバイトの採用のために、4名から5名の社員が、3時間のワークショップを実施する。
一般に、アルバイトの採用というと、疲れた顔をした店長が1名出てきて、10分程度話して、「で、いつからバイトにこれる」と言われ、即採用というのが関のヤマだが、この会社は違う。
採用にきてもらった人を「ハッピー」にすることがポイント。歌あり、劇あり、グループワークあり・・・様々なオモシロおかしい課題をこなして、A社の組織文化に適合した人を探していく。
このような「選抜」の仕組みは、ハーバード大学のハワード=ガードナー(Harward Guardner)が「多重知能理論(Multiple Intelligence)」の中でふれていた「Evaluation in situ(状況における評価)」の仕組みに共通するかもしれない。
人間の知能は決して、標準テストで測定できる単純かつ均質なものではない。多領域に広がる人間の知能を測定するためには、リアルな状況を設定し、そこでのパフォーマンスを多面的に評価することである。もちろん、それは負担やコストが大きいかもしれない。が、標準テストのみに依存し「不適当な人」を選抜し、そこからもたらされる弊害を考えれば、トータルのコストは安いかもしれない。
採用活動が終わったあとは「オリエンテーション」だ。ここでは、A社のもつ強烈な組織文化を、いかに新入りのアルバイトに伝えるか、そこに適合させるかに苦心する。
組織文化への適合といっても、「強制感」のともなう無理矢理な話ではない。自然に巧妙に、組織文化の「学習」が進行する。
採用にしても、オリエンテーションにしても、ある意図に基づき、巧妙に、かつ綿密に組み立てられたプログラムに従い、進行する。聞けば聞くほど、そのプログラムは、よくデザインされていて、驚いた。
部屋の温度管理、かかっている音楽、スタッフの立ち振る舞い・・・すべてがデザイン対象であり、アルバイトが一人前になっていくことを支援する「要素」である。
---
来週には、これとは異なるアプローチで、組織文化の「学習」を行っている企業を訪問させていただく。「語り得ぬもの」は、いかに伝えうるのか。
そして人生は続く。
ちなみに週末は修士論文口頭試問。ということで週末なし。
嗚呼、人生は続く。
---
追伸.
午前中、某社との共同研究のため六本木へ。某社の方々、そしてM先生との打ち合わせは、インプロヴィゼーション(ジャズの即興)のようでいて、面白かった。非常に早くフレームワークが決まった。