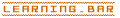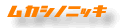村上春樹氏「走ることについて語るときに僕の語ること」を読んだ!
村上春樹の最新刊「走ることについて語るときに僕の語ること」を読んだ。
筆者自身がいうように、本書はメモワール(個人史)である。「走ること」を基調テーマとして、村上氏は「自分の人生」を語り、「老い」を見つめる。
村上氏にとって、「書くこと」を支えているのは「走ること」である。「走ること」を通して、「精神と身体の健全さ」を維持しようとしている。
---
誰かに故のない(と少なくとも僕には思える)非難を受けたとき、あるいは当然受け入れてもらえると期待していた誰かに受け入れてもらえなかったようなとき、僕はいつもより少しだけ長い距離を走ることにしている。
いつもより長い距離を走ることによって、そのぶん、自分を肉体的に消耗させる。そして自分が能力に限りのある弱い人間だと言うことをあらためて認識する。(中略)
黙って飲み込めるものは、そっくりそのまま自分の中にのみこみ、それを(できるだけ姿かたちを大きく変えて)小説という容物の中に、物語の一部として放出するようにつとめてきた。
(p36より引用)
---
氏も文中で述べていることだが、「創造すること」「創作すること」は、自分をヴァルネラブルな立場に追いやる行為であり、ある種、不健康で、破壊的な行動である。
かつての文壇には「小説家=不健康で破壊的な人間」というイメージが確かに存在していたが、それは創造という活動がもつ破壊的側面に由来するものと思われる。
「創造」を行えば、いわれもない場所から、いわれのない角度で、いわれのない非難を受けることもある。「非難する方」は「数百万人いる読者の一人」であり、彼らの立ち位置は常に「安全なホカホカとした場所」にある。
彼らは自分一人が何か異議を申し立てたとしても、「アイツは傷つかない」と思いがちである。しかし、それはウソだ。このことは、一度でもヴァルネラブルな立場に身をおいた人間なら、誰でもわかることである。
氏は「走ること」で何とか精神のバランスをとってきたのだろう。「走ること」で肉体を追い込みつつ、「黙って飲み込めるもの」は、何とか自分の胸に抱きしめて。
しかし、彼の「走ること」にも否応なく「老い」の影がしのびよる。老いは、平等に、静かに、かつ、じっくりと我々のもとを訪れる。
---
四十代も半ばを迎えてから、そういう自己査定システムが少しずつ変化を見せ始めてきた。
簡単にいえば、レースのタイムが伸びなくなってきたのだ。年齢を考えれば、これはある程度仕方のないことだ。人は誰しも人生のある時点で身体能力のピークを迎える。
(p24より引用)
▼
僕は今、五十代の後半にいる。二十一世紀などというものが実際にやってきて、自分が冗談抜きに五十代を迎える事なんて、若いときにはまず考えられなかった。(中略)
そして現在、僕はその「想像もつかなかった」世界の中に身をおいて生きている。
(p33より引用)
---
年をとるということは、若いときには「想像もつかなかった世界」に、まるごと自分が「投げ込まれること」を意味する。「身体能力のピーク」を過ぎ、手をこまねいて見ていれば、「創作のクオリティ」にも陰りが見え始める。それは、ある意味で、致し方ないことだ。
ゆえに、若いときには「意識すらしなくてもできたこと」に心を配らなければならない。どこぞの雑誌のキャッチコピーである「必要なのは若さではなく技術」ではないけれど、老いを迎えたあとには、生きるための「工夫」や「智恵」がどうしても、必要になってくる。
---
ただ、僕は思うのだが、本当に若い時期を別にすれば、人生にはどうしても優先順位というのものが必要になってくる。時間とエネルギーをどのように振り分けていくかという順番作りだ。
ある年齢までに、そのようなシステムを自分の中にきっちりこしらえておかないと、人生は焦点を欠いた、メリハリのないものになってしまう。
(p49引用)
▼
若いときなら、たしかに「適当にやって」いても、なんとかフルマラソンを乗り切れたかもしれない。自分を追い込むような練習をやらなくても、これまで貯めてきた体力の貯金だけで、そこそこのタイムは出せたかもしれない。
しかし、残念ながら僕はもう若くはない。支払うべき対価を支払わなければ、それなりのものしか手に出来ない年齢にさしかかっているのだ。
(p79引用)
---
若いときには「適当にやってやれたこと」も、年をとるとそうはいかない。しかるべき時に「支払うべき対価」を支払い、かつ、優先順位を決めて、時間とエネルギーを配分することが求められる。それは、長距離ランナーがペース配分をするのに、ちょうどよく似ている。
誰かがそっと囁く。
「なぜ、そこまでして走るのか?
あなたは十分に走ったじゃないか。
もう歩いて楽になればいいのではないか?」
しかし、村上氏はそれでも走る。「昔と同じような走り方」はできないかもしれないけれど、「少なくとも最後まで歩かずに」
---
タイムは問題ではない。今となっては、どれだけ努力したところで、おそらく昔と同じような走り方はできないだろう。その事実を進んで受け入れようと思う。あまり愉快なこととは言い難いが、それが年を取ると言うことなんだ。
(p164)
▼
もし僕の墓碑銘なんてものがあるとして、その文句を自分で選ぶことができるのなら、このように刻んでもらいたいと思う。
村上春樹
作家(そしてランナー)
1949-20**
少なくとも最後まで歩かなかった
(p233)
---
僕はハルキストでもなければ、熱心な小説の読者でもない。しかし、本書は「走ること」への洞察を通して「生きること」について深い、だが、押しつけがましくない示唆を与えてくれた。
「走ること」を強制するのでもなく、かといって、その「虚無」を訴えるわけでもない。いつもながらに、筆致の絶妙なバランスには舌をまく。
「少なくとも最後まで歩かなかった」
あなたなら、墓碑銘に何と刻むだろうか?
何? まだスタートラインに立ったばかりだって?
---
追伸.
TAKUZO、いまだ熱下がらず。40.7度。カミサンは献身的な看病を続けている。僕もダウン。土曜日までは、何とか踏ん張らなければ。気合いだ。
昨日は、朝、病院に早く出かけて並んだ。診察開始前だというのに、すでに5から6人の親子が並んでいた。
前にも言ったように、幼い頃、僕は本当に病弱だった。父が、家をはやく出て、病院の受付に診察券をだす。それから母や祖母が、僕を抱いて病院にいった。もちろん、僕に記憶はないけれど。
それから30年弱・・・そのとき親がどんな気持ちだったか、ようやく僕にはわかった。
そして歴史は繰り返す。