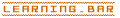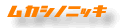ヴィゴツキーを「実践」する!?
ロシアの心理学者にレフ=セミョノビチ=ヴィゴツキーという人がいる。教育学をやっている人なら、知らないでいることが許されない学者の一人だ。ジャン=ピアジェと並んで、20世紀にもっとも影響を与えた心理学者の一人だろう。
ヴィゴツキーの提唱したセオリーに最近接発達領域(Zone of proximal development)というのがある。
この理論には様々な解釈があるけれど、一般には、子どもが「自分ひとりでできること」と「自分より有能な他者に助けられてならできること」の「間」のことをいう。ヴィゴツキーは、この「間」に「発達」や「教育」の可能性を見た。
子どもは、より有能な他者に助けられ、支援を受けることで、この距離を縮めることができる。この心理的距離が徐々に縮まることこそが、「発達」ということになる。
より有能な他者としては、対象者が「独力でできること」を見極め、適切な支援をしなければならない。「支援が足りない」のは困るし、「支援をしすぎ」てもいけない。この頃合いが難しい。
---
僕は、ヴィゴツキーのアイデアを、知識としては一応「知っている」。しかし、それを「知っていること」と「実践すること」とは、全く別のことである。
たとえば、愚息の場合。
フォークに食べ物を注意深く刺してやり、彼の手にもたせれば、それを使って、何とか食べ物を口に運ぶことができることを、僕は知っている。
しかし、仮にそうすれば、彼は3回に1回は、フォークを振り回して食べ物を落としたり、フォークそのものを落としたりするだろう。「独力でさせること」はかえって面倒を生む。
「ええぃ、面倒くさい、オレが食べさせたるわ」
生来イラチな僕は、つい手をだしてしまう。最近接発達領域の「距離」を無視してしまう。
どこで読んだのか忘れたけれど、
「船長は血が出るまで唇をかむ」
という格言があるらしい。
上にたつ者(船長)は、手を出したくなる衝動を唇から「血」がにじむまで、こらえることが必要だ、という教訓である。人を育てる上で、イラチになってはいけない。
もちろん、逆に「これくらいはできるだろう」とふんで、思い切ってさせたことが、全くの検討違いだったこともある。おかげで愚息はアタマを強打。大泣きされたことも一度や二度ではない。「ごめんね・・・」と平謝りである。
子どもだけじゃない。職場でも同様。
時に僕は「言い過ぎ」、時に僕は「言い足りなく」なる。
---
「知っていること」と「実践できること」は違う。
ヴィゴツキーの本を読むたび、ため息まじりにそう思う。「最近接発達領域」の含意するところは、本当に奥深い。