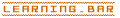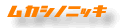Teacher proof : どんな教師でも使えちゃう性
耐教師性(Teacher proof)という言葉がある。一言でいえば、「どんな教師でも使えちゃう性」。
一般に、カリキュラムや教材などを論じるときに使われる言葉で、「あの教材、耐教師性が高いよねー、だよねー」というと、「どんなに経験の足りない教師でもすぐに利用できるように設計されている教材だよねー」という意味になる。
例にもれず僕の「うろおぼえ」で恐縮だけど、確か、耐教師性は、1950年代から1960年代のアメリカ、いわゆる「モダン教育学」で頻繁に用いられた言葉であると記憶している。
モダン教育学は、耐教師性の高い教材や学習原則を、大学の研究者が開発し、実践者が実践現場でそれを利用する、という図式で研究が進んでいた。
しかし、それが1980年代にはいって批判され、いわゆる「ポストモダン教育学」が生まれる。ここにおいて「耐教師性」という言葉は、いわば「時代遅れの」「いにしえの」概念として、忘れ去られた。
その後、教育学では、アクションリサーチなどの方法論が主張されるようになる。アクションリサーチは臨床的に「その場の、その問題」を実践者と研究者が協働で解決することがめざされるプロセスコンサルテーションである。そこには、かつてのダイコトミーである「研究者と実践者」の役割分業は - 少なくとも理念的には - 薄まっている。
---
しかし、僕は思う。
80年代の批判を通して、「研究者と実践者の非対称な権力関係」は再構築をせまられてもよいことだったのかもしれないが、「耐教師性」は本当に「忘れ去られてよかったことだったのか」と。
教育とはいつの時代も、個別具体的な現象である。故に、「その場で生まれた、その問題」を解決することは、正しいと思う。
しかし、そのようにして生まれた革新的な教育環境は、おうおうにして、研究者の手を離れた時点で、うまくいかなくなる。あるいは、当該研究者の属するコミュニティを離れて実践されることが、そもそも試みられない。こうした事態は、自戒を込めていうが、研究の現場では頻繁に起こる。
この問題を指摘されると、僕なんかは「痛いなぁ」とアタマを抱えてしまい、「モゴモゴ」と口ごもってしまう方なんだけど、対応は人によって異なる。
普及や一般化といったモダンの概念に関しては、「興味がないと裁断すること」、あるいは、「その場で生まれた、その問題にこだわること」が、研究者としてコレクトな態度とされる傾向もないわけではないように思える。
もちろん、先に述べたように、「耐教師性」を志向しようにも、それが実現できる保証はない。しかし、だからといって、それは「あきらめてよいもの」であったかと問われれば、僕は、どうしてもそう思えない。
---
今から10年前。まだ僕が学生だった頃、耐教師性は「60年代の遺物」として教えられ、当時の僕は、何の疑いも持たず、それをアタマにたたき込んだ。
それから10年・・・かつて折り合いをつけたはずの概念に対して、今なお、逡巡してしまう自分がいる。