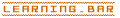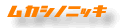「小さき者へ」 重松清著・・・
「家族」「父親と子ども」を問う作品を世に問い続けている作家、重松清の「小さき者へ」を読んだ。家族の物語を集めた短編集。
親と子ども、そして夫と妻でさえも、時に理解不能に陥る。言葉を紡げばつむぐほど、その言葉は空中を宛もなく彷徨う。相手のすべてが腹立たしく思えてくる。昨日までうまく回っていた家族は、ある日突然機能不全に陥る。そして、そうした事態は、どの家族にも起こりえる。
しかし、動揺し、音をたてて崩れていきそうな家族の果てにあるのは、単なる虚無や絶望ではない。
絶望の淵に片足をとられても、もう片足は、地にある。一歩前に足を進める。その一歩が実りあるものになるかどうかは何人たりともわからない。家族関係の編み直しは、今はじまったばかりである。
「あとがき」で、重松は言う。
---
坂道はしばしば人生や世間の厳しさを伝えるときのたとえ話に用いられる。下り坂はたいがい転げ落ちるものだし、人が生きることは、長い長い坂を上り続けるようなものだとも言われる。
(中略)
でも、建物の中はともかく、外の世界で完全に平らな場所なんてどこにある? 僕たちの立つすべての場所は、程度の差こそあれ、傾斜している。僕たちは皆坂道にたたずんでいる。だから、重心は前後左右に微妙に揺れ動く。それでも、そのバランスの悪さを飼い慣らして、平気なふりをして立っている。体もも、たぶん、心も。
(中略)
「問題が何も解決していないじゃないか」としかられることの多い、僕のお話の中でも、本書の六編はとりわけ「解決しなさかげん」が際だつものとなった。(中略)でも、それが僕の考える生きることのリアルだ。そして現実のキツい購買から逃れることのできない彼や彼女たちが、物語の最後で踏み出した一歩は、坂を下るのではなく登るための一歩であってほしい、と祈りながら書いた。
---
今日も、日本全国の家庭では、大人と子どもの苛立ちが続く。
「オマエの気持ちはよくわかる。でも、オレがオマエくらいの頃は、こんな風じゃなかった・・・もっとしっかりしていた。今から、そんなことでどうする。この世の中をどうやって生きていける? オレが死んだ後、オマエはどうやって一人で生きていく」
「わかったふりをしてほしくないね。オレがムカツクのは、わかってくれない父さんじゃない。わかったふりをしている父さんなんだ」
いつまでたっても両者の苛立ち、そして「わかりあえなさ」は消えないのかもしれない。唯一できることがあるのだとしたら、その窮屈で、胸を押し殺されそうな、この状況から逃げずに向き合うことだけなのだろうか。
「わかりあえなさ」を抱きしめて、生きることなのだろうか。
その境地、今の僕は、そこにいない。
僕には正直にわからない。