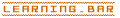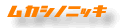親父
どんな会話の流れの果てに、そうすることになったかは忘れたけれど、帰省中、僕が「親父」をマッサージすることになった。
「そこにうつぶせに寝て」
ぶっきらぼうに僕は言う。親父は決まりが悪そうに、それに従った。
しかし、その次の一瞬、僕は言葉を失う。
親父の腰、背中、首を触って、すごく驚いた。指が筋肉に全く入っていかない。そこは鉄板のように堅く、部分によっては盛り上がっている。
僕も筋金入りの「肩こり」症である。しかし、これは自分以上だ。自分以上に、筋肉が緊張している人間に、久しぶりに出会った。
---
親父は、電話交換機の技術者として北海道の電話事業を支えてきた。アナログからデジタル、携帯電話、IP電話・・・めまぐるしく変わるテクノロジーの中で、学び続けた人であった。ここ数年は、札幌で出向生活をしていたが、今夏、また現場に戻った。
仕事はオモシロイらしいが、どうも腰痛がひどく、首も痛いのだという。
1時間にわたって、親父をマッサージしながら、僕が一番最後に彼の腰、背中に触れたのは、いつであったかを考えた。
それはおそらく、20年くらい前のことではなかったと思う。子どもの頃、父の日か何かに「肩もみ券」をプレゼントしたのが、最後ではなかっただろうか。誰もが一度は、やってみたいと思う贈り物の定番である。「肩もみ券」は1回か2回試されたものの、やがて、親父の机の奥深くに消えた。
その後、僕は思春期を迎え、18歳には北海道をでた。
世間一般の父親と息子がそうであるように、僕と親父も、たまにあっても、それほど長い会話を交わさなくなっていた。
決して関係が険悪であったというわけではない。そういうものなのではないかと思う。もちろん、父親の体に触れることは皆無であったといってもよい。
---
おそらく20年ぶりに親父の体に触れる。その硬直した筋肉を揉みほぐそうとした。
過去の記憶は曖昧である。子ども時代、彼の体が、そこまで硬直していたのかどうかは記憶にない。
しかし、ひとつだけ確かなことがあるのだとすれば、それは、僕が今手で触れているものが、40年にわたる労働の結果、何者も受け付けなくなってしまった鋼鉄のような腰、背中、首であるということであった。
どの家にも受難の時期があるように、うちにも大変な時期もあった。今だから笑って話せることもある。その時でも、彼は働き続けた。否、働き続けるしかなかったのだと思う。その結果を、今、僕は手に感じている。
何とも言えない時間だった。テレビでは紅白歌合戦をやっている。僕の知らない歌手が、僕の知らない歌を、歌っている。
「これからは体に気をつけてください」
とだけ、心の中で呟いた。
来年、また帰省しようと思う。