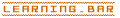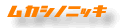多様化・多忙化・複雑化する大学院ゼミ!? : 古典を読まなくなることで失われる「思考の文脈」
先だって、論文を書かなければならなくなって、ドナルド・ショーンの「Reflective Practicioner」を、本当に久しぶりに読み返す機会を得ました。
最初は、論文執筆のために必要な箇所、8章だけ(組織学習に関する章ですね)を読もうと思ったのですが、久しぶりに読み返してみると、
「おー、こんなことも言っていたのか!、なんと!」
と思うところがあまりに多く、結局、大方の章を読み返すことになってしまいました。
久しぶりに、何とか、そのような時間がとれてよかったと思っています。まさに「スルメ」のような大著です。
▼
ところで、大著を読んでいて、痛切に思ったことがあります。それは、「多様化・多忙化・複雑化する大学院でのゼミ運営」で、指導教員としての自分が、ついつい「古典」をやむなく、ないがしろにしていた、という事実です(1980年の本で古典とは、申し訳ない気持ちもたっぷりなのですが、敢えて、ここではそう呼称します)。
ワンワードでいうと、「これはいかんな」と少し反省しました。汗顔の至りです。
具体的にいうと、かつての中原研では、夏に合宿を行い、集中的に古典的大著をみんなで読む時間をつくっていましたが、ここ2年は、やんごとない事情で、その慣習を廃止していました。「理由に該当する正当性のある理由」はないのですが、敢えて述べるのだとすると、3つくらいの状況から、やむなく、そのような判断をとりました。
理由のひとつは「メンバーの多様化」です。
今や中原研のメンバーは、学生から社会人大学院生、そして、仕事との両立をはかっている人から子育て中の方まで、年齢含めて、非常に多様化しています。
そういう多様な方々を対象にして、いっせのせで、時間をあわせて集中的に時間をつくることが、年々、難しくなってきた、ということが、まず背景としてあります。
ふたつめの理由は「研究の複雑化」です。
最近は、定量データの取り扱い、定性的な研究手法まで、非常に分析の手法が高度化・複雑化してきており、それを「実践の中から学ぶ」ために、ゼミ生個人の研究とは別に、「研究室の研究」を任意でつくり、それに従事していく中で学ばせる手法をとっています。
研究は常に「進歩」していきます。そして、その進歩のスピードが格段に速くなっている。何とかかんとか、それにおいつくための時間を確保することが非常に年々難しくなっている印象があります。「Publish or Perish?(論文を書くか、滅亡するか?)」という言葉がありますが、とにかく早く業績をだすことが優先される風潮が高まっています。
みっつめの理由は、指導教員である僕の「多忙化」です。
かつては夏休みといいますと、比較的2ヶ月くらいは余裕があって、その間に合宿をすることは不可能ではなかったのですが、それが段々、年々と難しくなりつつあります。
何とかしなくてはならないのはわかっているのですが、現段階でも、夏・秋の休み中に、スケジュールのない土曜日・日曜日は全くない状況です。
かくして、中原研では、「古典は各人が任意で読むように」ということになったのですが、それが各メンバーにおいて、どの程度、完遂されているかは分からない状況になってしまいました。
▼
ところで、今回、30年以上前に書かれたショーンの大著を読んで、痛切に思ったことは、誤解を恐れずにいえば、この本は「Reflection in Action(実践の中での内省)」を扱っているだけの本ではない、ということです。
わたしたちは、ショーンといいますと、わたしの研究領域の研究者ならば「知らないでいることを許されない概念」のひとつである「Reflection in Action」を真っ先に思い浮かべますが、「古典を読まないことで失われるがち」なのは、この概念が出てくるまでの「歴史的文脈」と「理論的文脈」なのです。
たとえば、「Reflection in Action」を知っている人の中でも、この概念の依拠する「歴史的文脈」と「理論的文脈」をご存じの方はどの程度いらっしゃるでしょうか?
原典をお読みの多くの方は、もちろん、ご存じの方も多いのだと思うのですけれども、ともすれば、そうした「歴史的文脈」と「理論的文脈」が滑落して、著名な概念である「Reflection in Action」だけが独り歩きしてしまいがちです。
・ショーンは、もともとデューイの「探究」概念を用いて、意思決定に関する研究をしていた
・ショーンは大学に来る前、長い間、NPOや組織において、組織革新に関するコンサルテーションや調査をしていた
・ショーンが大学にうつってから、専門職養成のカリキュラムの編成に苦労し、その中から「専門職」について考えることになったと思われる
・「Reflection in Action」の着想を論じるデータとなったものに関しては、「建築家・デザイナーの会話記録」「精神分析の会話記録」「工学教育の学生協働プロジェクトのデータ」「ビジネスにおけるマネジャーの思考プロセス」「トランジスタ研究開発の会話記録」「都市開発の建設計画における専門家の会話記録」などがある。決して「教師」や「医師」の意思決定を扱うだけのモデルとして、「Reflection in Action」が着想されたのではない。
・ショーンが「Reflection in Action」において常に意識していたのは、「組織学習」に関する問題であった。つまり、組織 × 専門職 × 意思決定の交差する場所に、「Reflection in Action」があった。
・
・
・
・
などなど。
こうして考えてみると、ショーンが提示した「Reflection in Action」という概念も、より立体的に見えてはきませんか。やはり、古典的大著をしっかり読まなくてはダメなのだ、と痛感しました。あたりまえのことではありますが。
▼
R.ローティなどを引用しながら、ポスト近代における大学の理念と存在意義の消失の問題を論じたのは、去年まで、同じ部門で働いていた元・同僚の藤本夕衣さん(現・慶應大学)です(「古典を失った大学―近代性の危機と教養の行方」というご著書があります)。
彼女がそのような主張を、ごくごく身近でしていながら(泣!)、ついつい、いろいろな理由で、古典をよむ機会をやむなく失わせていたことを、反省しています。
問題はどのように、その時間をつくるか、です。
もう一度、初心に戻って、考え直してみたいと思っています。
そして人生は続く
投稿者 jun : 2014年5月27日 06:21