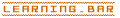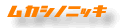疾患と病い:アーサー・クラインマン著「病いの語り」
医師は、病気を「疾患(desease)」と捉えるが、「患者」にとって、それは「病い(illness)」である。
こう喝破したのは、ハーバード大学医学部の精神科教授でもあり、人類学部の教授でもあるアーサー・クラインマンであった。
アーサー・クラインマン
http://fas.harvard.edu/~anthro/social_faculty_pages/social_pages_kleinman.html
「病い」とは「個人が病気に関してもつ意味」、すなわち「物語」のことである。それは、自分の病気を患者が「語る」なかで構成され、いったん構成されてしまうと、患者の人生の中のあらゆる出来事の意味を統御する効果をもつ。
対して「疾患」とは「生物医学的な構造や機能の不全」である。たとえるなら、「胸の痛み」が「急性大葉性肺炎」に換言されるとき、「病気」は「疾患となる」ことになる。
---
本書において使用する「病い(illness)」という用語は、「疾患(desease)」という用語とは、根本的に異なったものを意味している。「病い」という用語を使用することで、私は、人間に本質的な経験である症状や患うこと(suffering)の経験を思い浮かべてほしいと考えている。
(同書 p4)
「疾患」は治療者の視点から見た問題である。生物医学的モデルの狭義の生物学的用語で言えば、つまり疾患は、生物学的な構造や機能におけるひとつの変化としてのみ構成されるということである。
(同書 p6)
---
医師は、患者との会話を通して、「病い」の中から必要な情報を抽出する。医師と患者との会話は、患者の訴える様々な痛みや不快の中から、「特徴的な症状」をよみとる作業でもある。
ドナルド=ショーンによれば、医師が医療の現場で出会う症例の80%は、教科書にのっていない症状を有している。
医療とは、「知っている事例」と「目の前にある患者が示す症状」のパターンマッチングではない。病いの中から、「症状」を抽出し、反省的かつ即興的に行われる意思決定行為である。
ちなみに、「特徴的な症状」は、過去の先行研究の中で、既に分類され、命名され、治療方法は標準化され、カタログ化されている。その背後には、ミシェル=フーコーのいう「権力」が、既に作動している。
患者は、医師の求めることがらを察知して答えることが、そもそも要請されている。それは明示化されていないものの、患者が自分にもたらされる便益を考えた場合に、果たすことを余儀なくされている義務である。それができぬ患者の症例は、「不定愁訴」になる。
患者との会話から抽出したデータに加えて、様々な医学検査を行って得たデータをもとに、病気の「原因」を同定する。それは、<科学的に物語を形成すること>でもある。物語は、永遠の「仮説」でもある。
僕の尊敬してやまない認知心理学者ジェロム・ブルーナーは、著書「ストーリーの心理学」の中で、法廷論争を「物語」に喩えた。それと同じことが、医学の現場でもおこっている。医師による「物語」の形成、それを世間では「診察」と呼ぶ。
しかし、「疾患」の「原因」がわかり、専門的な「診断」がついたとしても、患者の「病い」は、必ずしも癒されるとは限らない。
病気の中には、「原因不明の病気」がある。あるいは、覚悟をもって、長いあいだつきあわなければ「慢性の病気」がある。そうした病気に苦しむ場合、この傾向はさらに強くなる。
医師にとって最大の関心は、「何が病気の原因で、なぜこの症状が生まれたのか」である。だから「診断」がつけば - つまりは医師の中で完結した「物語」が構成されれば - 医師の立場では、ひとまずは満足である。
しかし、「患者」の関心は「この病気が治って、元通りの生活が営めるか、どうか」である。一言でいえば「治るか、どうか」。病気の「原因」は、わかるにこしたことはないが、医師ほど関心があるわけではない。極端なことを言えば、「原因」がわからなくても、「治ればよい」。
---
患者と医師の関係は、信頼関係(ラポール)があればOK,とか、そういう「甘い」ものではない。
そこは「物語の闘争」の現場である。しかし、その闘争は「絶望」ではない。
最後にアーサー・クラインマン自身が、医師見習いのときに経験した物語をもって、今日のエントリーを終える。
---
1960年代のはじめ、医学の2年目と3年目に在籍していた私は、数人の患者に出会った。(中略)
最初の患者は7歳の痛々しい少女で、ほとんど全身におよぶ重篤な火傷を負っていた。彼女は渦巻く水の中につかり、皮がむけ広がった傷口から火傷組織をピンセットで引きはがす治療浴に連日耐えなければならなかった。
この経験は彼女にとって恐ろしく辛いものだった。少女は叫び声をあげ、うめき、医療チームの努力をかたくなにしりぞけて、もうこれ以上痛い目にあわせないように懇願した。
かけだしの臨床学生としての私の役目は、少女の火傷を負っていない方の手をにぎって、できるだけ元気づけなだめながら、レジデントの外科医が、生命を失い化膿した皮膚繊維を、うず巻く水浴槽のなかで、すばやく引きはがすことができるようにすることであった。浴槽の水は、すぐに淡い紅色にかわり、やがて濃い血の色に変わった。
連日の恐ろしさに私はほどんと耐えられなかった。少女の叫び声、血液で汚れた水中に漂う生命を失った繊維、皮膚をはぎとられた肉、出血が止まらない傷口、清潔にしたり包帯をしたりすることをめぐる戦い。
そんなある日、やっと気持ちが通じるようになった。
考えあぐね、自分の無知と無力に腹をたてて、その小さな手をしっかりとつかむこと意外に何をしたらよいのかもおぼつかず、彼女の容赦ない苦しみに絶望したすえに、私はその少女に尋ねていたのである。
あなたはどのように苦しみに耐えているのか?
こんなにひどい火傷をして、連日連日ぞっとするような外科的処置を受けるのは、どんな気持ちなのか話してもらえないか。
彼女はかなり驚いた様子で、呻くのをやめ、変形のため表情を読み取ることも難しい顔でこちらを見つめ、それから単刀直入な言葉遣いで、わたしに語った。
話しているあいだ、彼女は私の手をいっそう強く握りしめ、叫ぶことも、外科医や看護婦を退けることもしなかった。(中略)
彼女は、患者のケアにおける貴重な教訓を私にもたらした。
それは苦痛の極にある患者とでも、実際におこっている「病い」の経験について語り合うことは可能であると言うことであり、その経験を整理するのに立ち会い、助力することが治療的意味をもちうる、ということである。
(同書より引用)
---
闘争の中にも「希望」がある。
投稿者 jun : 2008年4月 3日 00:01