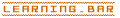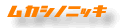米山公啓著「医学は科学ではない」
米山公啓著「医学は科学ではない」を読んだ。
表紙の要約文が本書の内容を的確に要約しているので、引用してみよう。
---
臨床の現場では、意外にも、医者の経験に基づく判断や勘で治療が決められたりしている。Evidenced based medicine(EBM)によって、治療や診断がおこなわれているのは医療行為の半分にも満たない。
---
本書では、上記の主張に基づいて、様々な事例、医療現場の実情が紹介されている。
医者の判断、検査がいかに曖昧で、学閥や薬価という様々な制約のなかで、それがなされているか、そして統計学を駆使した様々な「平均医学」が、いかにあてにならないかを紹介している。
EBMの考え方が成り立っている欧米でさえ、医療のうち5割程度しか、EBMでしかないのだそうだ。
再現性があるということを科学の条件とするならば、名医が存在するという現実は、医学の非科学性を示しているということになる
という筆者の指摘が印象的だった。
---
さて、下記は私見。ワタクシメは、専門家ではないので、いつものように無責任に発言する。
まず、筆者のように「科学」の定義を再現性に求めるのならば、「医学は科学ではない」というセンセーショナルなタイトルをつけたくなるのかもしれない。
が、EBM的な診断も一部には限定適応可能だそうなので、控えめに謙虚にタイトルをつけるとするならば「科学的に医療をおこなうことは結構難しい」になるのではないかと推察する(こんなタイトルの本は売れないな・・・)。おそらく、それは真実だろう。
だからといって、大規模疫学調査等の実験計画法に基づく「科学的な探求」を放棄するのに妥当な理由は見あたらないのではないかと思った(そんなことは著者は当然わかっている)。
科学的に明らかにできない部分があることは認めつつ、その限界を把握しつつ、「それでも」、わかる部分を見つけることが妥当な態度だと思う。
一言で言うならば、「いろいろ言われるけれど、ないよりは100倍マシなことが多そうだ」と言えるのではないだろうか。
これは、医学であろうと、教育学であろうと、人にかかわる学問に関しては、すべてに言えることだと思う。
「人」に関する場合、科学的に明らかにできない部分は、アートであろうと、職人芸だろうと、折衷するほかはないと思う。「恥知らずの折衷主義で何が悪い」という態度を決め込む他はないし、そこを恥じるべきではないと考える。
だけど、一般にはこういう「折衷主義」は嫌われる。人はわかりやすい議論を好む。つまりは、「科学的な態度」か「代替科学」か、「サイエンス」か「アート」か、「サイエンス」か「理念」か、みたいな一見もっともらしく見えるダイコトミーに陥りやすい。こういうのを僕は「振り子的議論」と呼んでいる。
「振り子的議論」はわかりやすいし、センセーショナルで、ストライキイングではある。だけれども、その失うところは非常に多いと思われる。
---
メモ.
アメリカ医療政策研究局の研究論文の評価システム
■グレード0
もっとも信頼できるもの。メタアナリシスにもとづくもの。
■グレード1
大規模なよく管理された無作為対照比較試験に基づくもの
■グレード2
小規模だが、よく管理された無作為対照比較試験に基づくもの
■グレード3
よく管理されたコフォート研究に基づくもの
■グレード4
よく管理されたケースコントロール試験に基づくもの
■グレード5
非比較対照試験
■グレード6
一致しないデータであるが、治療指針作成に有用であると考えられるもの
■グレード7
専門家の意見に基づくもの
---
投稿者 jun : 2006年12月29日 05:00